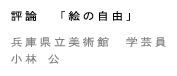
大阪の信濃橋画廊での個展のおりだったと思う。
このときにはもう、街中の光景を映した写真に由来するモチーフと、
たっぷりとつくられた余白と、飄逸な線描という、今にもつづく美崎慶一の代表的な
様式の作品が壁にかかっていた。
鮮やかな緑などの色彩と余白のまぶしい白さから、
日差しの強い夏の日の光景を連想しながら在廊中の作家にたずねたのは、
そうした光景につかずはなれずの関係で住まう、
線描によるモチーフを描く際のスリルについてだった。
スリルというのは、写真的、つまり映像的再現的描写とは位相のことなる線描を
最後に描き入れるという作画のプロセスを想像したからで、それは紙や絹を
支持体とする水墨画と同じようにやり直しのきかない一発勝負の仕事であるはずだった。
それまでにつくってきた画面を壊して、そうして絵画を完成させること。
そんな風にその時は形容したように記憶している。
美崎氏の返答についてはっきりとは思い出せないのだが、
にこにこと生意気な若輩の評を聞いてくださっていたはずだ。
2018年の夏、このたびの京都での個展に出品予定の作品と、
これまでの仕事について改めてお話を聞いた。
時間を追って作品の変化をたどると、線描こそが美崎氏の本領であり、
その魅力を絵画として成り立たせることが一貫して問われ、
試みられてきたことが良くわかる。
これは美崎氏の作品を継続的に見てきたひとには自明のことだろう。
ただ、21世紀に入ってから美崎氏の作品を見はじめた私には、1993年の美崎氏の
初個展のDMに掲載された線描による男性像はとくに強い印象を残すものだった。
一筆書きのように途切れることなく縦横に引かれ、渦を巻き折れ曲り、
積み重なる線が生み出すボリュームと空間の確かな手ごたえ。
それが圧倒的であるだけに、この線描があらわれる絵画空間に色彩を
導き入れることには困難がともなうのだと美崎氏は素直に語ってくれた。
抽象的な色面よりも、
近作に見られるような映像的な再現描写(ただし何らかの方法で断片化された)の方が、
つまりイメージとしての様式が異なる(先ほどの言い方をすれば「位相の異なる」度合いが
高い)ものの方が、線描と同居した際に絵画的強度をもたらすというのは
不思議といえば不思議であるが、それはおそらく映像的な再現描写が、
線描にとっての単純な背景ないし「地」としておとなしくしているわけではなく、
それぞれが互いの出方をうかがっているような、
そんな一定の緊張をたもった関係でいるからこそだ。
そしてすぐに付け加えなければならないが、そこにもうひとつ、
余白という3つ目の役者も存在するから、
緊張関係というのも単純な二者の対立構造にはとどまらない。
余白はこの二者を切り離し結び付ける媒介であり、
かつ自らが省略されたイメージであることを知らせ読解をうながしもする。
画面は凪いでいるようでいて、隙はない。
映像的なモチーフは画家の取捨選択によって、
余白として大きく消し去られたり、輪郭を失い周囲と融合したりすることによって、
現実の光景の断片から絵画的要素へと変性される。
そうした画家の操作が、夏の日が生み出すコントラストの強い景色、
あるいは白トビしてしまった写真のような光景を連想させるのだろうが、
実際には光学的な現象とは無関係に、絵画的な判断によってイメージとして
描かれる部分と余白として消去される部分とが取捨選択される。
当初は一つの作品に一つの視点からの光景が招き入れられていたはずだが、
2017年の個展では一つの画面に複数の視点から得られた光景が混在するようになった。
この変化により映像的モチーフに向かう視座は一点に定めることができなくなり、
絵画空間の複雑さは飛躍的に増した。
ただし、この異なる位相の光景もまた余白によって媒介されるので、
画面の端正なたたずまいは失われない。余白は空白ではなく、
そこにいかなる光景が補完されるべきかが見るものに問われ続ける場として
積極的な役割を帯びている。
10年ぶりくらいかもしれないが、改めて線描を描く際のスリルを思い浮かべながら、
線描を描き入れる手前の作画を行っているときの心持をたずねると、
早く線描を描き入れたくてたまらないのだと美崎氏は答えた。
もちろん線描に至るまでのプロセスが、単なる作業に過ぎないというわけではないだろう。
ただ、三つの要素の三すくみにも似た緊張感が絵画としての完成をもたらす、
その瞬間を画家が一番の楽しみとしていることは良くわかる気がする。
それに近い感覚のものがあるとすれば、
料紙装飾と書との真剣勝負ではないか、などと私の空想は広がっていく。
これまで呑気に「絵画として」などと書いてきたが、
美崎氏の絵画空間には透視図法や視点の併置、見立てによる余白の読み替え、
イメージが喚起する意味の連鎖といった多種多様な要素が
(場合によれば「絵画」の夾雑物とみなされるものが)さりげなく共存する。
白トビした写真が見せるのは日差しの強い夏の、
ラチチュード(許容範囲)をはみ出した光量がもたらす事物の輪郭が溶けた世界だ。
しかし画家は、太陽よりも強い光を手に入れた。
彼は写真には許されない奔放さで見慣れた光景を余白に置き換え、
招き入れた線描とともに絵の自由を謳歌する。
兵庫県立美術館学芸員
小林 公
